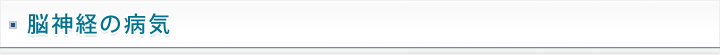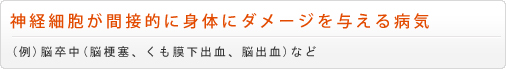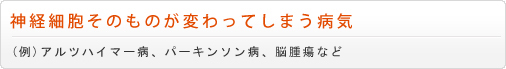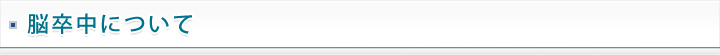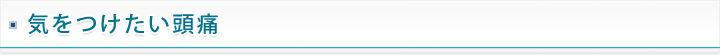脳神経は身体にとって最も重要な箇所です。
これらに起こる病気は、体内で無数につながる神経細胞がダメージを受けることで起こります。
その種類には以下のようなものがあります。
ここでは特に予防が効果的な脳卒中についてお話しします。
脳卒中とは、脳血管の障害による疾患の総称。脳梗塞、くも膜下出血、脳出血などが含まれます。脳血管の障害というのは簡単に言えば脳の血管が破れたり、詰まったりすること。血管が詰まった状態になるのが脳梗塞で、破れた状態になるのがくも膜下出血や脳出血といった病気です。
脳卒中が起こる前触れには、手足が動かしづらい(片側の場合が多い)、反応が悪い、目が見えない、言葉が出ない、頭痛、めまい などが挙げられます。これらの症状が急激に出現したら脳卒中の疑いがあります。
以下に示すのが脳卒中の危険因子。これらの危険因子がある方は注意が必要です危険因子を危険因子のまま放置せず、少しでも改善するよう努力することで脳卒中のリスクを少なくできます。
高血圧
収縮期血圧が140mmHg以上、あるいは拡張期血圧が90mmHg以上であれば高血圧と診断されますが、血圧レベルが高ければ高いほど脳卒中の発症率は高くなります。
糖尿病
糖尿病は脳梗塞の発症を2〜3倍高くします。血糖コントロールが重要です。
脂質異常症
高コレステロールや高中性脂肪で脳卒中の発症リスクが高まります。
喫煙
喫煙は日本や欧米でも脳卒中の有意な危険因子です。とくに脳梗塞やくも膜下出血で発症率が高まります。
心房細動
不整脈の一つですが、命にかかわる脳梗塞をきたしやすい疾患であり、早期発見、早期治療が必要です。
北里大学の全国統計によると、慢性反復性頭痛がある人は全体の40%におよびます。頭部打撲やその他の一過性の頭痛まで含めると、ほとんどの人が頭痛を経験しているのではないでしょうか。ただし、頭痛にもさまざまな種類があります。大きく分けると機能性頭痛と症候性頭痛に分けられ、それぞれ「一次性頭痛」「二次性頭痛」と呼ばれています。機能性頭痛は、片頭痛、緊張性頭痛などが含まれる「頭痛持ちの頭痛」のこと。近年片頭痛予防の内服薬や注射が開発され、極めて高い有効性が示されています。頭痛に対する鎮痛剤を繰り返し内服すると、そのことで頭痛が増加するという悪循環に陥らない様にすることが肝要です。
症候性頭痛は、頭部外傷や脳腫瘍、くも膜下出血、感染症など脳神経内科や脳神経外科の治療の対象となる頭痛が含まれます。
ご心配な方はお気軽にご相談ください。
頭痛というのは「脳の障害」と考えられている患者さんがほとんどです。しかし脳そのものは痛みを感じることはありません。 頭痛の多くは頭蓋骨の外側の筋肉や血管、末梢神経への刺激、または頭蓋骨の内側で脳を走る血管や膜への刺激が原因です。
頭痛は心配のいらないものがほとんど。しかし危険を知らせる重要な警報となることもあります。以下の頭痛の場合は注意が必要 です。早めにかかりつけ医に相談しましょう。
激しい頭痛
突然起こった頭痛
長時間続く頭痛
徐々に強くなる頭痛
意識障害を伴う頭痛
めまいや嘔吐感を伴う頭痛
高熱を伴う頭痛
けいれんを伴う頭痛
麻痺やしびれを伴う頭痛
言語障害のある頭痛
視力低下、物が2重に見える頭痛
朝の頭痛(目覚め型頭痛)
普段と異なるような頭痛が起こった場合は、早めに病院を受診し、CTやMRI検査を受けておくとよいでしょう。